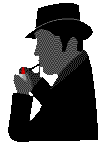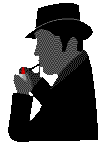第一話
第1章 俺がホストというものを知った日
俺が初めてホストの存在を知ったのは小学校4年生の時だった。風邪で学校を休んで、ベッドで目が覚めて見ると、母親は買い物に行ったらしく家には誰もいなかった。午後のどんよりした空気の中、退屈でテレビをつけてみると、午後のワイドショー番組をやっている。50人くらいの人達がボタンを持って後ろの掲示板に得票がでる番組。よくある番組のはずだった。しかし、何か違和感が感じられる。普通でない異様な感じ。子供の目には単なる中年のおやじが司会の質問に応えている風景が映っているはずだが、どこか違う。画面全体に異様な雰囲気が漂っていた。『これらの人は普通の人じゃない!』小学生の俺にも分かった。妙に惹かれるものを感じ、パジャマのままテレビの前につっ立っていた。
画面に登場するおやじ達・・・目つき、顔つき、髪型、スーツの着こなし方。「結婚している人は何人いますか?」「奥さんは今の仕事をしていることは知っていますか?」司会者の声をぼんやり聴きながら、最初は何が何だか分からなかった。ただ異様なものを感じるだけ。だんだん分かってきたのが『この人達は女の人を接待する仕事なのだ』ということだけ。良く分からないが、番組を見ているうちに体が異常な興奮を感じた。母親が帰ってきたので、何が何だか分からぬまま、その番組や仕事のことを話した。しかし母親は何か汚らしいものを見るような顔で、「そんな仕事を知る必要はありません」と怒った。
そのことは、そのまま幼い記憶に刻みこまれたまま月日が立った。
映像に興味を抱いて映画の専門学校に通いはじめた頃。金はないが時間だけはあった。小遣いだけでは満足できないし、何かバイトでもしたい。そんなある日、たまたま見たスポーツ新聞に「ホスト募集」という求人欄を見た。『これはどんな仕事だろう?』どこか子供の頃の記憶がよみがえったのかもしれない。何か「ホスト」という言葉に惹かれるものを感じた。友人にも相談したが、誰も経験者がいないので何もアドバイスを得られず、とりあえず惹かれるままに行ってみることにした。新聞には「6時以降に電話してください」と書いてあった。
新宿2丁目に着いて場所確認の電話をしてみる。聞いたとおりに行ってみると、そこは小さな雑居ビルだった。中にエレベーターもない。3階まであがって廊下に出ると、異様な男がタバコを吸いながら立っていた。世の中にこんな気持ち悪いセンスの持ち主がいるのか、というような男が。ひょろ長い長身に緑のスリーピース。パンツは腿のあたりがぴっちりして、膝下がものすごいフレアの入ったパンタロンに踵の高いブーツ。幅広の襟に肩には大きなパットが入っている。昔のエルビス・プレスリーがステージ衣装のまま出てきた?それともルパン3世の真似?その衣装に金髪に横わけでロングにした男がこちらを見た。見るなり「君?面接に来たの?」「まぁ、入りなよ」と愛想笑いを浮かべている。

スナックの入り口のような安っぽい木製の店のドアをあけると、すぐ右隣に小さな小部屋がある。その小部屋に店の経営者らしい男が嬉しそうに座っていた。当時はホモという存在がよく分からなかった。ピンクのスーツにひらひらのドレスシャツ。胸元が大きく開いていて毛むくじゃらの胸毛がのぞいている。つるつるした脂ぎった肌で鼻のあたりが赤く、髭剃りあとが青々としている。その割に髪の毛が薄かった。男はおしゃべりで、ずっと話つづけていた。どうやら店の説明をしているようだが何を言っているのか良く分からなかった。男は短足を少しでも長く見せようかと踵の高い靴を履いている。おぼろげながら「男が男に買われることは法律上では何も問題がない」というようなことを言っているようだ。俺は普通のホストクラブに来ているつもりだったから、意味も分からず、ただ不思議な異空間に呆然としていた。
「とにかく1日中、何も言わずに座っていればいいから」と店の中に入るようにいわれた。店内はワンルームの一室のような狭い部屋。待合室のように部屋の周囲は安っぽい椅子が丸く敷き詰めており、そこに少年が20人くらいずらっと並んで座っていた。「ここに座りなさい」と言われるままに一角に腰かけた。『やばいな。これは早いとこ逃げ出さなきゃ』と思った。『トイレに行くふりをして逃げるか?タバコでも買いに行くといって逃げるか?』とにかく様子を見ることにした。隣の同い年くらいの少年に声をかけてみた。それで、初めてこの店の実態を知った。
「ここは2丁目のホモ連中が男を買いにくる店。客は店側に1万5,000円払って、店が5,000円、自分達に1万円入るというシステム。要するに客は店で少年を指名して外へ連れ出してホテルに行く、そこでケツを貸す」という店らしい。そういうことをする少年達は殆どホモでも何でもない普通の男達だが、話を聞くと「別にいいんじゃない。一発で1万円入るんだから。いいアルバイトじゃない」と笑っている。店は朝の8時までやっているらしい。「たまには女もくるよ。水商売の淫乱な女が」とも聞いた。女が来ると聞いて妙に興奮するものがあった。
そのうち、廊下にいたひょろっとした男は店長らしく「いらっしゃいませ」と愛想のいい声が入り口から聞こえた。入ってきた客はでぶの禿げオヤジ。しかし、女装しているわけでもホモ風でもおかま風でもない。一見不動産のオヤジ風。しかし腹はおもいっきり出ている。でっぷりしたオヤジは店長に店の中央のテーブルに案内された。いかにも常連らしく、すぐに小太りの少年を指名して水割りを飲みはじめた。しばらく談笑していたが、突然その小太りの少年が男の腕や肩を揉みはじめた。「君、なかなかうまいねぇ」なんて男は上機嫌でいっている。少年が「ホテルでも、マッサージしてあげようか?」と言うと、男は満面の笑みを浮かべて、すぐに立ち上がり、連れ立って店を出ていった。
客も来ないし、俺もそろそろ引き上げようかと思ったら、妙に油ぎったガマガエル顔の短足オヤジが入って来た。初めて来たらしく、しきりに店長に店のシステムを確認している。ガマガエル顔から出る赤い舌が妙に艶かしく、まるで蛇のようにチロチロと出たり入ったりしているように見える。店長とそのガマガエルが同時に俺の方を向き、手招きする。俺はどうして良いか分からず、硬直した。
続き
|