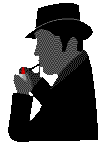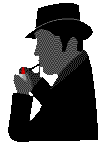第四話
世は暴走族、そして女子大生ブーム。デパートでルイ・ヴィトンのバックが売れ、BMWが巷に目に付くようになってきた頃だ。日本はバブル前夜、空前の好景気の足音が聞こえ始め、誰もが奇妙な興奮に包まれつつあった。街は人であふれ返り新宿・渋谷・池袋、どの街も活気があった。しかし、そんな世間の景気の良さとは無縁の俺には金がなかった。俺は一週間後再び店を訪れたのだけれど、ホストクラブで働く決意をした理由は、結局金のためだった。
新宿ジゴロの店内。目の前に二人の男がいる。ひとりはピンク、もうひとりはブルーの髪の毛だった。この得体の知れない宇宙人のような男たちはこの店の人間である。ピンクの男がぺぺ。ブルーの男はマサトと名乗った。年は俺と大差ない。不思議なことに、店にはこの二人しか従業員がいなかった。彼らは見透かしたように説明する。「あのね、この近くに今日、新店が出来たんだよ。ザ・ジゴロって云ってね。ココよりずっと大きい店なんだ。皆、そっちに刈りだされてる、だからココは俺たちだけ・・・。」
ぺぺとマサトは暇つぶしと俺の新人教育を兼ねて、俺にホスト談義を始める。「いいかい、ココの稼ぎだけじゃ金にはなんないよ。裏金・・・。まあ、簡単に言えば女に金を貢がせるんだよ・・・。」ド派手なピンクのクルクルパーマのぺぺがそう云うと、マサトが話を続ける。ナンパしろ、とにかくナンパだ。それがホストの必修条件だという。そして名刺を作ること、それを毎日50枚は配ること。キャバレーやソープ、水商売の女のところに客として行って自分を売り込め、そしてその女を客として店に連れて来い。
直毛の青い髪を掻き分けながら、マサトはさらに云う。
「ひとりの女・・・たとえばソープ嬢が1日幾ら稼ぐか知ってるか?平均で7万。多い奴は20万は稼いでるよ・・・。その金の半分、いや9割が自分の金になると思いな。」
そして二人は不敵な面持ちでこう云った。
「愛を売ってるんだよ。それが俺たちの商売なんだ。」
俺はぺぺとマサトの話に衝撃を受けた。ここでなら金が稼げる。いつか見たテレビの光景が頭をよぎった。きらびやかでゴージャスなホストたちと自分の姿がダブる。マサトは最後にこう云った。
「女を騙すんじゃないだ、惚れさすんだ。間違えちゃいけないよ。」
俺はここで仕事をする気持ちが一気に高まっていた。
「さて、じゃあ仕事だ。まず厨房に入れ。」
とペペが云う。俺は料理も酒も作ったことがない、と云うと二人は、
「1週間もしたら新人が来る、そしたら交代させてやるから、大丈夫だよ。とにかくやってみろ。」
と云ってとりあってくれない。
厨房の中に入り、調理器具や皿グラスの前で何をしたらいいのか全く分からず、呆然としていると、男が入ってきた。俺より1時間後に面接を受けて働くことになった遊(ゆう)木(き)という男だった。彼は
「大丈夫、俺バーテンやっていたから。」
と頼もしい事を云う。そして手際よく彼は働き出した。俺は彼に言われるままに手伝ったが、実際に調理や酒を作るのは全て遊木がやってくれた。仕事がひと段落したとき、彼と話をした。年は俺と同じ。社交的で気さくな奴だった。
今は住むところが無い。仕事は水商売やバーテンで生活してきたという。足元を見ると履いてるブーツの裏底が剥がれ、それをガムテープで止めている。彼も俺と同じで金が無いのだった。そんな彼はやがてナンバーワンホストになるのだが、それはまだ先の話だ。
その日は3人ぐらいしか客はこなかったが、俺と遊木は朝まで店で働いた。遊木がどこに帰ったのかはよくわからなかった。俺は日常からかけ離れた世界に片足を踏み入れたことに、奇妙で言葉にならない期待と不安で一杯だった。
翌日出勤すると、いきなりぺぺとマサトがこう言い出した。
「この店は今日で閉店だ。明日から新店のザ・ジゴロへ移ってもらう。」
突然の話に驚いていると、俺を面接したあのスニーカー清が現れた。
「おい、人手が足んないんだ。新人はいないか。」
大きな声で叫んでいる。
厨房にやって来て、「お前ら名前は?」と聞く。俺は当時、尊敬する映画監督・黒澤明の名前を、源氏名に使っていたので、
「クロサワです。」
と名乗った。遊木が自分の名前を言うと、スニーカー清は俺と遊木をジロリと見てから、
「よし、遊木来い!」
と言った。遊木とスニーカー清はそのまま店を出て行ってしまった。一時間とはいえ先輩の俺を差し置いて、遊木が「指名」されたことに俺は腐ったが、仕方がなかった。その日俺は、厨房で前日遊木に教わったことを思い出しながら何とか仕事をこなすことが出来た。
厨房で仕事をしながら、俺の頭の中は新店での仕事を夢想していた。グラス洗いなんか今日まで。こんなボロ店ともオサラバさ・・・。
まだ見たことも無い新店ザ・ジゴロではあったが、俺には大きなチャンスが来た手応えがあった。そうだ、これが俺の生きる道なんだ。そう確信し始めていた。入ったばかりのホストという世界に、誰よりも大きな野望を秘めながら、俺は黙々と1人でグラス洗いを続けていた。
続き
|