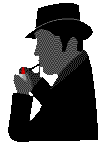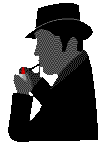第五話
第2章
新宿ジゴロの衝撃③
新店「ザ・ジゴロ」は、いわゆる中箱(店の規模のこと。大箱はキャバレー、大型クラブ、中箱はクラブ程度、小箱はスナック程度)で、天井には豪華なシャンデリア、壁は全部金ずくめ。もの凄くギラギラ輝いていた。その上、顧客の席ごとに仕切りも金の鉄板のような板で遮られており、顧客どおしが顔を合わさない配慮がされていた。その仕切りには、筆文字で大きく「男」、「金」、「欲」など、様々な漢字が描かれていた。中央奥には、ヨーロッパ映画に出てくるハーレムの蓋付ベットを思わせるシールドで覆われた席があり、VIPルームと言われる席があった。この席は経営者の伏見直樹が顧客を連れてきた時か、32万円のルイ13世のボトルを入れると支払いは70万円程度になるが、それを入れた顧客の席として使用される。
そこではじめてTVで観た伏見直樹を見た。身長180cmくらいで、金髪の髪を7:3に分けており、女性を思わせるような甘いマスクだが、どこかオーラを感じるものがあった。
店のホストは全員紺のパイロットスーツ。襟と肩に3本のラインが入っている。スーツの襟は幅広に広がっており、ズボンはパンタロン、誰もより足を長く見せようと踵の高いブーツをはいている。そして、背中には漢字一文字を入れることが義務付けられ、金の刺繍で「忍」、「男」、「心」、「恋」、「愛」など思い思いの文字が描かれていた。スーツ自体が同じ色で統一されているため、それぞれが裏地を工夫し、馬の絵やら寅や竜など豪華にして目一杯アピールするようにしていた。
ワイシャツは襟部分が4.5cmありWボタン。カフス部分もカフスが豪華なのはもちろん、袖に薔薇の刺繍を入れたり、ネームを入れたりして派手にし、競って独創性を強調していた。
当時のスーツはスーツの襟幅が広いのが流行で、迫力があり、胸板が厚く見えるとのことで、肩パットを入れてウエストを目一杯に絞り、逆三角体系に見えるように工夫が施されていた。その後、西洋も含めて一般のスーツも肩パットでウエストが絞られたものが出るようになったので、ホストのスーツは当時、流行の最先端をいっていたのかもしれない。今ならグッチやイヴサンローランにもパンタロンスーツもあり、美脚スーツとかあるが、20年前はホストのスーツ以外は見られなかった。ホストはそれぞれがより足を長く見せる、スタイルを格好よく見せることに心血を注いでいた。
新人の俺には、まだパイロットスーツは作らせてもらえなかったが、後日、俺のを作った際は色は黒、背中の文字を英語で「Gigolo License」とし、伏見直樹に「お前は相当センスがあるね」と褒められた。「紺のスーツ、背中には一文字漢字」と義務づけられていたわけだから、本来は怒られるはずなのだが、「すばらしいよお前は!」と褒められた。ホストの世界は目立とうという気持ち、独自性が尊重された。
この店でも初日から厨房をやらされた。スタッフは総勢30名程度、毎日10〜20人の新人が入り、厨房以外にもボーイをやらされたり、フロント、煙草などを買いにいくパシリとして使われるが、毎日大量に辞めていった。
店のNo.1のバンビ田宮が替え歌を歌っていた。周辺の女達は楽しそうに手拍子をとったりしている。聞いてみると「ジゴロハイスクール。やる気は充分、やるのは15分。貢いでください。カルチェにダンヒル、ルイビトンに・・・貢いで欲しいから」と歌っている。『俺にガンガン貢げって、そんな歌を歌って、一体誰が貢ぐ気になるのか?』と疑問に思った。理解に苦しんだ。しかし、数日後、それは体で理解できた。
要はお客は、それぞれ自分だけは客じゃない、と思っている。歌を聴いて女は笑いながら「他の女への歌ね。私のことじゃない。私は彼の女で、客じゃない。自分以外のお客さん・・・しっかり貢いでね。本命は私だけなんだから」と思いながら、しっかり貢がされているんだ、ということが。ホストはみんな「俺はお前だけに本気で、他の女とは仕事で付き合わされているだけなんだ」と思わされているんだ、と。
店は連日満員。顧客はソープ嬢だったり、AV女優、キャバクラ嬢、銀座のクラブの女だったりする。酒は当時二万五千円のレミーマルタンが流行っていたが、ヘネシーで三万円、サントリーのVSOPが一万二千円、一番下のリザーブが八千円という価格。レミーマルタンはブランデーで、本来、ストレートで飲むものだが、ブランデーグラスに氷やクラッシュアイスを入れて飲んでいた。本格的に酒を楽しもう、という客は殆どいなかった。
一週間くらいの厨房の仕事だったが、ついに本格的にホストの仕事をさせてもらえる日が来た。
スニーカー清の席に着かされた。相手の女性は30代前半くらいのソープ嬢で、物凄く売れていたらしい。ピンク系のスーツ、赤毛の髪で大きな瞳の長い睫毛にはマスカラが塗られ、赤い鮮やかなルージュが妖しかった。スニーカー清も上機嫌そうに「こいつ、新人だから宜しくね」と紹介してくれた。俺は前につきながらお絞りの出し方、コースターの使い方、水割りの作り方を教わっていた。
スニーカー清が呼ばれて別の席に移動した。俺は、何を話して良いのかどきどきした。女は何か話すのかと俺の目を悪戯っぽく覗き込んだ。俺は何か話さなければ、と焦った。ここで女を退屈させたらお終いだ。舌がカラカラだった。相手に自分の緊張を悟られないよう、水割りで軽く喉を潤ませて、さも話しなれたようにゆっくりと声を出した。
「お仕事は、何をされているのですか?」
とりあえず彼女の情報を入れようとさぐりを居れた、つもりだった。
女の大きな瞳がいっぱいに開かれ、一気につり上がっていった。そして、いきなり黙ったままバックを掴むと出口に向かった。俺は呆然と立ちすくんだ。スニーカー清が小走りに彼女のところに向かった。
女はスニーカー清に何か怒鳴っていたが、しばらくドアの外で話していたようだ。何が何だか
分からないまま俺は呆然としていた。
数十分後くらいか・・・ 店に戻ったスニーカー清が、一気に俺のところに凄い形相できた。
首根っこを持ち上げられてロッカールームに引きずり込まれた。俺の両襟を締めながら「俺の客に何てことを言ったんだ?お前は俺を潰す気か?」と怒鳴った。顔が上気して真っ赤だった。俺は何のことか分からずおろおろと視線を宙にさまよわせていた。
「お前は、さっきのお客が1日どのくらい稼ぐか知っているのか?1日20万円は稼ぐんだ。その分の保証はできるのか?」俺は何も分からなかったが、スニーカー清の説教は1時間以上続いた。俺は相当めげた。これは相当慎重に取り掛からなければならない。言葉ひとつも選ばなければならないんだ。言っていいことと悪いことがあるんだ。これはしっかり体に刻まれた。
後で分かったのだが、ホスト用語に「爆弾を入れる」という言葉がある。爆弾とは、指名されているホストとお客との仲を悪くさせたり、駄目にさせること。体を売って仕事している女に「仕事は何をやっているのか?」は絶対にタブーで、偶然、俺はスニーカー清に「爆弾を入れてしまった」ことになった。しかも、女の稼いだ金は総てスニーカー清の懐に入っていたらしい。女が潰れたら清に金が入ってこないことになる。清の怒りはただごとではなかった。
この店でホストデビューした初日にいきなり手痛いミスをしてしまった。
続き
|