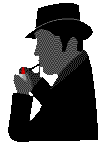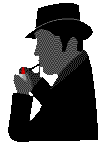第十一話
第5章 ヘルプ生活③
バンビ田宮の連れてくる客の友人・知人など直接指名以外の客は「枝(えだ)」といい、自分の営業ができる客である。そうした客を自分の指名客にしたりして、徐々に自分の顧客が増えてきた。そうなるとバンビ田宮の面倒を見ながら、自分の顧客への営業もあり、店以外でも仕事は徐々に忙しくなってきた。
店は大体朝の8時ごろまで開いているが、いつも自分の客が2~3人、閉店間際まで残っていた。店が終わるとアフターとなり客と食事して帰るのだが、皆、自分と食事したいと思っているし、他の客と行くんじゃないか?と疑っているので、帰すのがなかなか難しい。それを「後で行くから…」とか言って無理やり帰すことになる。
アフターは、大体が焼肉屋だった。焼肉を食べて客をタクシーまで送り、車に乗せた後、次の客が待っている喫茶店まで行って相手をする。時には客の家まで行ってやる。家まで行って話をして、添い寝をしてやる。客は大体が風俗関係の仕事をしている女達で、SEXは、仕事で再三しているから求めない。それよりも、安らぎを求めている。その安らぎを癒すには添い寝が一番いい。大抵の男は、腕枕を続けていると、腕が痺れてきて長時間続かないものだが、腕がしびれても続け、決してはずさない。それで何とか女が寝付くと、次の客の家に向かう。
また、少しでも時間が空いたら、電話をかけまくる。店が終わって電話、寝る前に電話、起きてから電話、朝昼晩といつも、電話をかけ続けることになる。寝る間を惜しんで働くわけだ。そうした睡眠時間が殆ど取れない生活を続けるのだが、中にはダンスや歌のレッスンに通っているホストもいる。自分の得意分野に磨きをかけるためだ。店に入って、掃除をした後、寸の間を惜しんでダンスの練習をしているホストも多い。
俺も何度か客に付き合わされて店で踊ることがあった。適当に踊っていると、伏見直樹から「お前もちゃんと習いに行かなければ駄目だ、授業料は自分への投資なんだから!」と言われたものだ。歌が得意な人間は、わざわざ手書きで譜面を作ってきてバンドに渡したりしている者もいた。
一般的にホストクラブに来る人間は、今までとんでもない、いいかげんな生活をしてきた人間が多いが、ここではみんな凄い努力家が多かった。結局は金のためなんだが、みんな血なまこになって頑張っていた。
ところで、店ではあるやり方を義務付けていた。普通の男は、みんな女性に対して優しく接しているのだが、その逆をやること。例えば、最初に会った女の子に「お前」という言い方をする。客がタバコを吸うときにライターで火を着けてやるが、自分がタバコを吸う時は、客に火を着けさせる。あるいは、平気で客に「お前なんか帰っちまえ!」という。
当時は、携帯電話なんかなく、ポケベルしかなかったので、連絡をとるためには、相手の電話番号を聞くしかなかった。街で女をナンパしても、当たり前のように「お前の電話番号は?」と聞く。「何で教えなくちゃならないの?」と応えるが、教えなければ悪い、という方向に話をもっていくのだ。
そうした時、昔のジゴロは、まるでヤクザのように強引だった。店は風俗の女性が多かったので、普段男にチヤホヤされている人が多い。そんなチヤホヤされている環境にいる女性に、わざとぞんざいに言うことで、逆に自分に惹かれさせてしまうわけだ。
午後はよく歌舞伎町にある王城という喫茶店にいたが、ある時、赤く染めた髪に、目鼻の整った顔だが化粧の濃い、いかにも夜のホステス風の女性が入ってきた。近くに寄るだけでも香水をプンプン漂わせ、服は原色のシャネルのスーツだった。それが、ツカツカと俺の近くに座った。気が強そうな女性で、きつい目つきで俺をにらみながらタバコに火を着けた。それを見て、俺は内心ビビリながらも、思い切って口を開いた。
「お前、何?ここら辺で働いているのか?」
相手は、驚いたようにポカンとしたような顔で俺を見た。しかし、相手が反応したので、かえって度胸が据わった。足を組み偉そうにふんぞり返りながら相手に対した。最後に名刺を出して相手の目の前に置き、
「俺は、ここの店にいるから、来いよ。明日来い!」
「分かった」
その日から、その女性は俺の太い(沢山お金を使う)客になった。後で分かったのだが、その女性は、ヤクザが経営しているボッタクリ店のヘルス嬢で、普段、「これじゃ足んないよ!ちゃんと払いな!」とか言って客のボーナス全部巻き上げるような女性だった。それが友人に「酷い男なのよ。はじめて会ったのにアタシのことを『お前!』扱いよ」と嬉しそうに紹介していた。
よくヤクザに、とんでもなく気が強いが綺麗な女がついているが、それは何故か?…実はSの女は、それより上をいく強烈なSの前だとMに変わってしまうのだ。伏見直樹は、そうした心理を利用して店のカラーにした。店も途中から「バイオレンスジゴロ」という店に名前を変えた。ホストは全員、九州男児のように男の中の男を演じるように努力した。最初、入店してきたナヨナヨした男も店で働くうち、徐々に染まって目の色まで変わっていくようになった。
ホストクラブという所にはヤクザからしょっちゅう脅しの電話がかかってくる。俺にも「俺の女に手を出したな?」という電話を何回か受けたことがある。そういう時は人一倍大きな声で恫喝する。
「おぅ!いい度胸じゃねぇか。手ぇ前ら、今から店に来いよ。勝負だ!こっちだって命張っているんだよ。ぶち殺してやるから、顔見せやがれ、この野郎!」
と怒鳴る。しかし絶対に相手は店に来ない。ヤクザも所詮仕事。どんなに喧嘩慣れしていようと、例えば気が狂った人間には自分も殺される可能性があるわけで、そういったリスクは避けることが多い。だから絶対に「すみませんでした」なんて相手に言わない。言った瞬間から相手の思う壺になるからだ。
その上、当時はホストをやりながらヤクザをやっている人間がいっぱいいた。あるホストクラブは、ホストの半分はヤクザだった。迂闊にホストを狙ったら、そのホストはある組の構成員だった、ということもあるのだ。だからヤクザもなかなかホストは狙わない。
ただ、新人ヤクザの最大の資金源は、女性に貢がせる金。一人二百万稼ぐ女性を数人抱えることで、その収入は相当額になるわけで、ホストはヤクザの仕事を妨害することになるから、言い合いや争いは絶えなかった。
ある日の朝、ポーカーハウスで、他のホスト仲間とポーカーをやりながら朝食を取っていると、いきなり黒服のヤクザが数十人ドカドカ入ってきた。そして向い側のあるホストにヤクザが群がり、そのホストを数人で神輿のように持ち上げると、一気に引き落とした。うめいてうずくまる男を引きずると外に連れて行き、店に横付けしていた黒塗りのベンツに乗せて発車させた。車が出た後、一人の男が戻ってくると、
「どうも皆さん、お騒がせしてしみませんでした。今、あったことは見なかったことにしてください。宜しくお願いします」
と言って一礼して出て行った。そうしたことを身近に目撃するほど歌舞伎町という街は異常だった。
また、俺と同じ店に、ある団体に所属しているホストがいた。イツキと言った。普段から、今でいえばマツケンサンバの松平健の衣裳のような金ぴかな上着を着ていて粋で華やかさをアピールしていた。身長もさほど高くないため、そうしたことで自分を目立たせようとしていたのかもしれない。そんな奴だったが、俺とは同期ということもあり、派閥は違ったが、親しくしていた。華やかな表向きとは別に、一人でホテルに泊まり俺に電話をかけてきて、「たまには一人になりたいんだ」という孤独な面もあった。
ある寒い日の夜、出勤のため、閑散としているホテル街をイツキは女と連れ立って店に向かっていた。前から黒服の男が一人、早足で近づいてくる。両手はコートのポケットに入っていた。イツキは、女に笑いかけ、隣をすれ違う男を軽くかわそうとしたが、男がよろけて肩が触れた。思わずイツキは「馬鹿野郎!てめぇ!」と威喝した。それに対し、男は「悪い、悪い、ごめんな」と薄ら笑いを浮かべて低調に頭を下げ、握手しようと左手を出してきた。イツキも、何気なく手を出し、男がイツキの手を強く握った。イツキが笑いかけようと男を見た瞬間、男は反対の右手をポケットから出すなり、炎と鈍い銃声が響いた。女は何が起こったのか一瞬分からず、隣を見ると、腕を組んでいる相手のイツキは血まみれになってうずくまるところだった。
救急車で青梅街道の病院に運ばれた後、女から店に電話がかかってきた。たまたま俺が出ると、イツキが内臓を激しく出血しており、輸血が必要で至急来て欲しい、とのことだった。女からの電話の背景にイツキの苦しそうな呻き声が聞こえてきた。
「痛い、痛てぇよ!ちくしょう」
俺たちは、仲間数人で病院にかけつけたが、出血多量で手遅れだった。
その件は新聞にも載らぬまま八百万円で手打ちが行われたらしい。
そんな街・歌舞伎町で、俺は運がいいのか、争いに巻き込まれることは少なかった。
ある日、いつものように客の女の部屋に行った。女は、部屋の中央にネグリジェのまま突っ立っていた。何となく空気が重く、俺が「どうした?」と聞くと、女は微笑むと奥の部屋を指差した。部屋を覗くと、身長一八五cmはあるごつい体系の男が、ベッドに腰掛けていた。40代らしき顔で角刈り、サングラスをかけていたが、その奥に射るような瞳が感じられた。
いきなりの対面だったが、『極道か?』と察した。その瞬間、背筋に冷たい汗がしたたり、さすがの俺もビビッた。
「お前がクロサワか?」
男は渋みのある顔で俺を見つめながら聞いた。俺が何も応えないので、男は続けた。
「こいつは、俺の女だから…」
男が言うと、俺は何も応えず、そのまま踵を返して部屋を出た。
翌日、喫茶店に呼び出しの電話がはいった。さすがに俺もヤバイと感じて、店が契約しているケツ持ちのヤクザに仲介を頼んだ。
約束の時間に風林会館にある喫茶店に行くと、この間の男が数人の男と待っていた。近くの席にこの間の女が赤いスーツを着て座っている。男は、どこかの組の組長だったらしい。それを聞いて、念のため仲介を頼んだヤクザに同行してもらった。実は、同行したヤクザとその男は友達(だち)同士だった。そのためか、話は終始穏やかだったが、男は低く渋みがある声で言った。
「お前、どうせ仕事だろ?なぁ、こいつに惚れているわけじゃないだろ?……だから降りろよ」
男の口元は笑っていたが、目が笑っていない。俺が応えないでいると男は繰り返し聞いた。
「仕事なんだろ?どっちなんだ?惚れてんのかよ?手前の本命女なのか?」
俺は乾いた口で応えた。
「仕事です。…だけど、惚れているんです」
「そうか…」
男は下を向いてタバコをもみ消すと、ため息を一つついた。
「まぁ、いいや。それはこいつ(女)に任せようじゃないか。俺はこれからも手を出すけどさ、お前も同じでいいじゃねぇか、どっちに靡くかの結論は、こいつ次第でさ…」
厳しい顔で睨まれた。この件は、その場で収まった。もっとも最終的に、その女は男と別れ俺の元に戻ってきた。実は男はその女の友達にも手を出していて、両天秤にかけていたことが分かったからだ。
続き
|